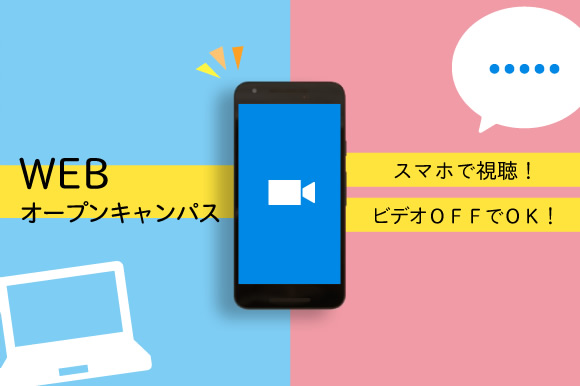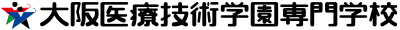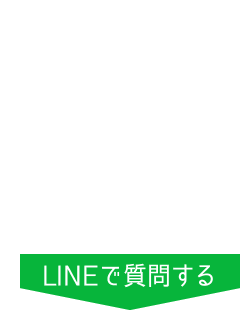ブログ
医療秘書になるには? 必要なスキル・資格を紹介| 大阪医療技術学園専門学校
2024.8.2
医療秘書とは、医師や看護師のサポートを主とする医療事務職のひとつです。
医療事務がおこなう管理業務、医師の予定管理や電話を含めた来客対応など、業務の幅は多岐にわたります。そのため、医療秘書になるには数多くのスキルと資格の習得が何よりも重要です![]()
しかし、医療秘書として就職する際はどのような教育機関を選べばよいか不安な人も多いのではないでしょうか![]() そこで今回は、医療秘書になるための流れを紹介します
そこで今回は、医療秘書になるための流れを紹介します![]()
目次
医療秘書になるには
一般的な秘書とは異なり、医療秘書は医療業界に属するため医療や医学の知識、事務処理能力が求められます。したがって、医療秘書として働くならば、現場で活かせる資格の取得が重要とされています。
医療秘書になるための流れ
先述したとおり、医療秘書は無資格でも問題なく就職できますが、資格やスキルがなければ即戦力として活躍するのは難しいでしょう。それでは、どのような手順で医療秘書を目指せばよいのでしょうか。以下で詳しく解説します。
1.専門学校や大学で専門知識を学ぶ
医療秘書を目指す学生は、専門学校や大学で医療に関する知識や技術を習得するのが一般的です。医療業界に特化した専門的なカリキュラムをとおして、疾病の原因や治療方法、診断手順などの医療知識を深められます。また、医療業務における必須のスキル、たとえばカルテ作成や入力方法、医療費の計算・保険請求の手続きなども習得可能です。
このように、医療秘書としてのキャリアをスタートするには専門学校や大学での教育が重要な役割を果たしています![]()
![]()
2.資格取得を目指す
医療秘書は未経験でも採用されるケースもありますが、医療に関する資格やスキルを持っている人、または経験者の方が圧倒的に採用に有利です。資格取得は自分自身のスキルアップだけでなく、採用担当者に医療業界で働く意欲や能力を証明できるよい手段です。
具体例としては、「医療秘書技能検定試験」、「診療情報管理士」、「医療情報技師」、「ドクターズクラーク」などがあります。
3.採用試験を受ける
医療秘書として働くには、病院や診療所が実施する採用試験に合格しなければなりません。それゆえ、自分が希望する条件を満たす求人情報があれば積極的に応募しましょう。なお、採用面接は医療関連の知識や経験なども質問されますが、ビジネスマナーも求められます。身だしなみや立ち居振舞いで減点されないように、ビジネスマナーは習得しておくべきでしょう。
4. 医療秘書として働く
医療秘書の雇用形態は正社員や派遣社員、アルバイトなど多種多様です。そのため、一日でも早く現場経験やスキルを身につけたい人は、派遣社員やアルバイトとして働くのも選択肢のひとつですが、福利厚生が充実しており、より雇用が安定しているのは正社員となります![]()
医療秘書になるために持っていると有利な資格
医療秘書になる際、特定の資格を有していれば就職活動で優位に働きます。それでは、具体的にどのような資格が有利になるのでしょうか。以下では、医療秘書になるために保有しておくべき資格を紹介します。
医療秘書技能検定試験
医療秘書として働くうえで、ぜひとも取得しておきたい資格は「医療秘書技能検定試験」です。本資格に合格すれば、医学的な基礎知識から医療秘書の実務や医療関連法規など、さまざまな知識が獲得できます。本試験は3級から2級、準1級、1級と4つのレベルに分類されており、3級や2級なら医療事務に精通していなくても合格が狙える難易度です。
なお、本試験は年2回開催ですが受験資格はとくにありません。だれでも気軽に受験できる点から、毎年多くの方が受験しています![]()
診療情報管理士
診療情報管理士は、患者のカルテ管理や診療情報の分析をおこなう専門職です。医療機関における患者の安全管理から経営への貢献まで幅広く携わるため、年々需要が高まっています。なお、診療情報管理士として就業するには、日本病院会と医療研修推進財団が主催する「診療情報管理士認定試験」に合格しなければなりません。
本試験の合格率は平成30年で66.3%、平成29年は44.5%と試験難易度は平均的なレベルです![]()
医療情報技師
医療情報技師は、医療システムに関する専門職となります。
診療現場での業務を理解し、医療システムに関する運営・管理を行います。新規システムの導入時には、ベンダとの調整役を担うこととなります。また、近年高まりつつあるセキュリティリスクなどの対応も行います。
医療情報技師が医療現場で活躍するために必要な資質としての専門知識が問われる試験となります![]()
ドクターズクラーク
医師の働き方改革の担い手として医師事務作業補助者に対する期待が近年高まっています。
医師事務作業補助業務に必要な医療文書の作成、医学・薬学、医療に関する法律・法令等の知識と技能が問われる資格となります。
秘書技能検定
秘書技能検定は、秘書に必要な知識やスキルだけでなくビジネスマナーや電話対応など、社会人としての能力を証明する資格としても人気があります。また、初級レベルである3級や2級は合格率が50%以上と、合格しやすい点も本試験が多くの人に受験される理由です。
医療秘書を目指す方はもちろん、これから社会に進出する新社会人にも秘書技能検定はおすすめの資格です。
医事コンピュータ技能検定試験
医事コンピュータとは「レセプトコンピュータ」とも呼ばれ、医療機関が診療報酬明細書の作成をおこなうシステムです。そして、医事コンピュータ技能検定試験はレセプトの作成や医療事務に関するITスキルを証明する資格です。
現代の医療現場ではIT化が進み、医療秘書の仕事も一定のITスキルが求められることから、本試験を受験する人が増えています。なお、こちらの試験もほかの試験同様、難易度ごとに分類されています。
診療報酬請求事務能力認定試験
公益財団法人日本医療事務協会が主管となり、実施している試験です。本試験に合格することで、優秀な医療事務としてのスキルが証明できます。医療事務として高いスキルが求められる病院などではとても重宝され、一部の就職先では「資格手当」が支払われることもあります。
しかし、合格率は30%程度と難易度が高く、だれでも簡単に合格できる試験ではありません。
電子カルテ実技検定試験
以前は、患者のカルテは医師が手書きで作成していました。しかし、現代では手書きではなく、電子ベースで保存するのが一般的です。こうした電子カルテを作成するために必要とされるのが「電子カルテ実技検定」の資格です。病院やクリニックなどの医療機関で働く場合は、この資格を取得しておけば即戦力として期待されるため、ぜひとも保有しておきたい資格といえます。
医療秘書になるために必要なスキル
医療秘書には資格だけでなく、必要不可欠なスキルも多々あります。以下で紹介するスキルを持っていれば、現場で期待される人材になる可能性は高まります。それでは、ひとつずつ詳しくみていきましょう![]()
コミュニケーションスキル
医療秘書として活躍するには、コミュニケーション能力が必須です。医療現場では医師や看護師、患者やご家族など、さまざまな人とのコミュニケーションが求められるからです。例をあげると医師のスケジュール管理や来客対応、電話応対など、コミュニケーションが求められる場面は数多く存在します。
したがって、多くの人と良好な関係を築くためにもコミュニケーションスキルは欠かせないスキルといえるでしょう。
状況把握スキル
医療秘書は、医師や看護師のバックアップとなる仕事を担当します。そのため、現場で起きている状況を冷静に把握し、何が求められているのかを迅速に判断できる能力が必要です。たとえば、医師や看護師が作成すべき資料があるとします。
しかし、患者数の増加や急患対応などで資料作成が遅れる場合は、医療秘書が資料作成をサポートすることで資料提出の遅れや提出遅延に伴うトラブルを回避できます。このように、状況を的確に把握し、適切に対応するスキルは医療秘書に欠かせない能力といえるでしょう。
ICTスキル
ICTスキルは情報通信技術の意味で、現代の医療現場では大変重宝されています。ICTとITは類似しているため、間違われやすいですが違いは明白です。ITは情報技術を指し、コンピューターシステムやソフトウェア、ネットワークなどの情報技術を指します。一方、ICTはITを活用して仕事や日常生活を豊かにする能力です。
遠方からでも家族を見守れるシステムの操作やタブレットを使用したオンライン会議など、日々の業務の効率化やコミュニケーションの円滑化に貢献します。このように、ICTスキルを身につければ、さまざまな医療貢献が果たせるため、価値あるスキルといえるでしょう。
医療秘書を目指せる学校の種類
医療秘書としてのキャリアを目指すなら、適切な教育機関で医療に関する知識や技術を学ぶのがおすすめです。しかし、医療に関わる教育機関は多数あるため、どの学校を選べばよいか悩んでしまう人も多くいます。ここでは、医療秘書が目指せる学校を紹介します![]()
専門学校
医療秘書になるための選択肢として、専門学校への進学が考えられます。専門学校では、基本的に2年間のカリキュラムで医療秘書として必要な知識や技術を効率よく習得できます。また、学習期間が短いため早く現場で活躍したい人には大きなメリットといえます。受講費用は、年間70〜100万円が相場です。
専門的な知識が学べるだけでなく、短期間で卒業できる専門学校は医療秘書を目指す方にとって有益な教育機関といえるでしょう。
大学・短期大学
医療秘書を目指すなら、大学や短期大学に進学する道もあります。大学の場合は、通常4年間の在学期間が必要です。在学期間中に、ビジネスマンとしての一般教育から医療に関連するさまざまな知識を学習できます。一方、短期大学は2年間の在籍期間が一般的で、こちらは大学と比べて実務により特化した内容に焦点を当てたカリキュラムが組まれています。
費用面については、4年生大学の場合は4年間で400〜450万円、短期大学であれば2年間で120〜200万円程度が相場です。ただし、これらの金額はあくまで相場のため、具体的な金額は各学校の公式サイトなどで確認するとよいでしょう。
医療秘書を目指すには専門学校がおすすめ
医療秘書を希望する人は、大学などで幅広い分野の知識を習得するのもひとつですが、専門学校という選択肢もおすすめです。ここでは、専門学校を選んだ方がよい理由を3つ紹介します![]()
基本的な資格から難関資格まで幅広く資格取得を目指せる
専門学校では医療秘書として必要となる基本的な資格から、より専門性を持って働きたい人向けの難関資格まで、さまざまな資格取得が目指せます。たとえば、医療秘書として保有しておきたい資格として「医療秘書技能検定」があげられます。本資格は、医療秘書としての基本的な知識や技術を証明する医療秘書ならだれしも保有しておきたい資格です。
このように、専門学校では資格取得をバックアップしてくれるため自身のスキルアップを目指す方には大きなメリットといえるでしょう。
正社員での採用・就職率が高い
専門学校は病院やクリニックと良好な関係性を維持しているケースが多く、豊富な求人が集まりやすい特徴があります。そのため、自分に適した就職先が見つけやすい点も専門学校を選ぶ大きなメリットです。
実際の医療秘書業務に特化した実習が学べる
専門学校に進学するメリットとして、医療秘書の業務を想定した実習が学べる点です。現場を想定した実習により、就職前に仕事内容が理解できるためです。また、実習で得た経験は就職活動時の面接でも大きなアピールポイントとなり得ます。
現場を想定したリアルな業務経験があれば、面接官も実際にどのような仕事を経験したのかが理解できます。仮に実習や実務を経験していなければ、想像でしか面接官に伝えられないためリアリティに欠けてしまうでしょう。
医療秘書になりたい人は「大阪医療技術学園専門学校」をチェック
本記事では、医療秘書になるための流れについて解説しました。医療秘書は医療機関における重要な専門職であり、高度な技術と知識が求められるため、就職するには医療分野に特化した教育機関で学ぶことが重要です。大阪市内にある「大阪医療技術学園専門学校」は、医療秘書を目指す多くの方から支持されている専門学校です。
本校の卒業生は14,000人を超え、医療や福祉業界の発展に大きく貢献しています。医療秘書を目指している方は、大阪医療技術専門学校のホームページをぜひチェックしてください![]()
新着記事
-
2025.7.16
-
2025.7.16
-
2025.7.16
-
2025.7.15
-
2025.7.15